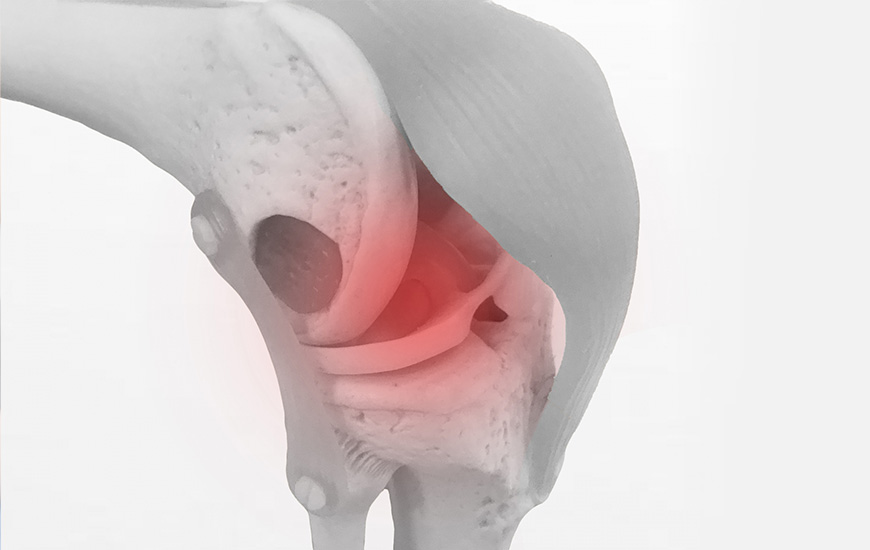目次
PRP療法とは
PRP治療は、患者自身の血液から抽出した多血小板血漿(PRP)を用いて体の修復が必要な部位に注射で治療する方法です。
PRPは成長因子といった組織の修復や炎症を抑えて痛みを改善する効果があります。PRPには種類があり、今回はPFC-FD、APSという治療も一緒に述べます。
| PRP | 血液からPRPを抽出し、患部に注射する |
|---|---|
| PFC-FD | PRPから成長因子を抽出・凍結乾燥し保存可能として、3週間後以降に注射する |
| APS | PRPを濃縮し、抗炎症物質(白血球など)と成長因子を高濃度濃縮。患部に注射する |
PRP療法のメリット
PRPは入院不要でブランクがなく、スポーツ選手に好まれます。手術とは異なり、治療後すぐに日常生活や競技に復帰できる点が大きな利点です。
また、体への負担が少なく、繰り返しの治療も可能です。
しかし手術を完全に回避できるわけではなく、すべてにおいて万能と言えるわけではありません。
①副作用のリスクが少ない
自分の血液を介した治療ゆえに副作用といったリスクが低い事が挙げられます。アレルギー反応が起こりにくいことから、薬に抵抗感がある方にも安心して治療できます。
②入院の必要がなく普段通りの生活ができる
入院については、手術で痛みを解決する場合少なくとも1週間以上は必要となってしまいます。
PRPは手術の代わりにはなりませんが、高度な抗炎症作用により疼痛を下げられる可能性があります。
生活への影響を最小限に抑えられる事が利点となります。
③治療痕が残りにくい
治療は膝関節への注射になりますので、傷跡という感じではなく一般的な注射の痕になります。
④慢性疾患にも効果が期待できる
PRP治療はスポーツ選手の外傷や損傷に対する治療として知られていますが、近年では変形性膝関節症の治療選択肢としても注目されています。
特に、改良版のPFC-FD(凍結乾燥血小板因子濃縮液)は有効性と安全性が報告されており、クリニックで広く使用されています。
大鶴らの研究では、変形性膝関節症患者302名にPFC-FDを単回注射し、12か月後に62%の患者で症状の改善が認められました。この結果から、PRP療法は慢性疾患にも一定の効果が期待できる治療法と考えられます。
⑤何度でも治療を受けることができる
PRP治療は繰り返し行うことができ、PFC-FDはフリーズドライ加工されているため、適切なタイミングで注射可能です。一般的に効果は12か月持続すると報告されています。
一方、APSは高濃度の成長因子や白血球を含み、血液採取から1~2時間で処理でき、採血当日に外来で治療が完結します。
APSは効果が2~3年持続する報告もあり、治療法の選択によって症状の改善期間が異なります。適切なタイミングで治療を重ねることで、改善した状態を維持できる可能性が高まります。
*松田芳和、JOSKAS Vol 46:589~596,2021
PRP療法のデメリット
特段大きなデメリットはありません。
この治療はメタアナリシスという分析では、ヒアルロン酸注射や、生理食塩水注射よりも疼痛及び機能の改善について有意に効果があり、リスクは他と変わらないと報告されています。*
しかし、費用が保険診療より高くはなってしまうため、他の治療で行っても効果が厳しいときに、検討されるといいと思います。
いきなり最初から勧める事は、私は行いません。他の治療でも効能があるかもしれないのに選んでしまうというのは患者様の希望なので尊重いたしますが、他の治療効果を知らずに選ぶのは費用という点において、一種のデメリットかもしれません。
*Chen P, J Orthop Surg Res 2019:14(1):385
①効果に個人差がある
効果には個人差があります。これは主に注射する患者様がみな同じ破壊程度の障害程度ではない事も影響しています。
慢性的な膝の痛みの変形性膝関節症において、PFC-FDという治療では12か月で62%の症状の改善がみられると報告があります。
逆に40%近くでは効果がないことも個人差を生む要因になっていると思います。変形性膝関節症が初期の障害に近い方では効きやすく、破壊が高度なgradeⅣという状態では効果がない場合があります。
*Tadahiko Ohtsuru,Knee Surgery,Sports Traumatorogy,Arthroscopy(2023):31:4716-4723
②腫れや痛みが起こる場合がある
APSという治療は、効果の持続時間が長い、濃縮したPRPを細胞とともに注入できるメリットがある一方で、白血球という細胞が炎症反応を起こしてしまい注射後の腫脹や熱感、痛みなどの有害事象が多いという報告もされています。
PFC-FDという細胞を含まないPRPの治療ではわずか1%程度の有害事象なので、「選ぶPRPによっては初期に腫れや痛みが起こり得る」という理解で良いと思います。
*松田芳和、JOSKAS Vol 46:589~596,2021
③感染症を起こす可能性がある
このリスクについては、ヒアルロン酸の注射とリスクが同等であることが、メタアナリシスという分析にて報告されています。このリスクについては「注射後の感染」も含まれております。
PRPだから感染症が起こりやすいということはないです。
*Chen P, J Orthop Surg Res 2019:14(1):385
④PRP療法が受けられない場合がある
PRP(多血小板血漿)療法を受けられない方はこのような方です。
- 血液疾患やがんの診断を受けている方
がん患者や既往歴のある患者には推奨されません。
血液を介した治療ゆえに血液に機能の問題 があると考えられるからです。 - 自己免疫疾患治療中の方
自己免疫疾患を有する患者では、PRPの成長因子が炎症を悪化させてしまう場合があり慎重に検討する必要があります。 - ステロイド薬を服用中の方
ステロイド剤を使用している方は、PRP療法を受けられないことがあります。
ステロイドがもたらす注射後感染のリスク上昇を懸念します。 - 患部に感染がある方
局所に感染がある方は、PRP治療を受けることはできません。 - 抗凝固薬を服用している方
ワーファリンなど抗凝固薬を服用している方は、PRP治療を受けることはできません。
これも薬による凝固機能変化によりPRPの効能に影響があるからです。 - 重度の糖尿病を患っている方
重度の糖尿病を患っている方は、感染症リスクの問題で、治療を受けられない事があります。
⑤保険適応外のため費用負担が大きい
自由診療なので費用については気にされると思います。
2025年3月段階で得られるデータです。
代表的なPRP療法として、PRP、PFC-FD,APSを例に挙げます。
それぞれについての費用の比較を提示します。対象は大学病院~クリニックまでの関東近県の医療機関における費用の調査を致しました。
価格は状況に応じて変化しますので、治療を考える方はその医院の価格を事前によく確認するのを勧めます。
| 治療法(医療機関関数) | 平均費用(万円) | 中央値(万円) |
|---|---|---|
| PRP療法(12) | 5.7 | 5.1 |
| PFC-FD療法(12) | 16.4 | 16.5 |
| APS療法(9) | 34.3 | 33.3 |
整形外科におけるPRP療法の流れ
PFC-FCを例にとって治療の流れを説明します。
- 受診の予約– 整形外科担当医の外来を予約
- 初回診察– 症状確認とPFC-FD療法の適応判断
- PRP外来(1回目)– 血液(約50ml)を採取、感染症検査
- 3週間待つ– PFC-FD製造期間
- PRP再生医療外来(2回目)– PFC-FD注射と経過観察
まとめ
PRP療法は、患者自身の血液を活用し、外傷や変形性膝関節症の治療に有効な選択肢です。入院不要で治療のブランクが少なく、繰り返し施術が可能な点が利点ですが、効果には個人差があり、腫れや痛み、感染リスク、費用負担がデメリットとなります。
PFC-FDやAPSなど、種類ごとに効果や持続期間が異なるため、適切な治療選択が重要です。
私は神経(脊髄)や膝を含めた整形外科手術の経験を持ち、MRIを活用した正確な診断と治療を提供することが目標です。
早稲田大学大学院の修士論文ではPRPを研究・論文化し、再生医療の可能性を追求してきました。患者様の痛みや悔しさを理解し、「笑顔」に変えられる治療を目指しています。
監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔
| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |
|---|---|
| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |
| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |
| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |
| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |
| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |
| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |
| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |
Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis
Spine Surgery and Related Research 3巻 2号
発行元 Spine Surgery and Related Research
65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について
脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討
C5/6 hyperflexion sprainの1例
上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例
人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例